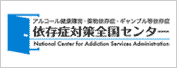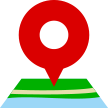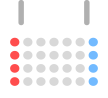Mindfulnessリサーチチーム
Mindfulnessプログラム
1. マインドフルネス精神病介入法 日本語版
(Mindfulness intervention for psychosis Japanese edition) MIP-J
精神病圏の患者の方が安全に瞑想ができるように作られているマインドフルネスプログラムです。瞑想の時間を短くし、分かりやすく簡単に実施できるように工夫されています。
[出典] : Tabak N T et al. Mindful cognitive enhancement training for psychosis : A pilot study. Schizophrenia Research 2014; 157: 312 - 313. ※著者の許可を得て翻訳
2. マインドフルネス尺度
- SMQ 日本語版 (Southampn Mindfulness Questionnaire) ※準備中
全ての方の不快な考えやイメージに対するマインドフルな態度を測定する自記式質問紙です。
[出典] : Chadwick P et al. Responding mindfully to unpleasant thoughts and images: reliability and validity of the Southampton Mindfulness Questionnaire (SMQ).
British Journal of Clinical Psychology 2008; 47: 451 - 455. ※著者の許可を得て翻訳
- SMVQ 日本語版 (Southampn Mindfulness Of Voices Questionnaire) ※準備中
精神病圏の患者の方の声または幻聴に対するマインドフルな態度を測定する質問紙です。
[出典] : Chadwick P et al. Responding mindfully to distressing voices: links with meaning, affect and relationship with voice.Journal of the Norwegian Psychological Association 2007; 44:581-588. ※著者の許可を得て翻訳
3. MIP-J用 宿題用紙
4. MIP-J用 瞑想音源データ (MP3) ※2019/09/27更新
- マインドフル チェックイン (5分)
- マインドフル チェックイン (7分)
- 呼吸瞑想 (10分)
- ボディスキャン (15分)
5. マインドフルネス依存介入法
6. マインドフルネス依存介入法用 瞑想音源データ (MP3)
- 山の瞑想
- 呼吸瞑想
- ボディスキャン
Mindfulness (マインドフルネス) 研修会
第2回 統合失調症・依存/嗜癖行動のマインドフルネス研修会
2021年春頃開催予定です。
詳細が決まり次第、順次ホームページに掲載します。
修了した研修会
【マインドフルネス基礎と実践】
第1回 精神病/統合失調症・依存/嗜癖行動のマインドフルネス研修会
大勢の方にご参加いただき無事終了しました。
- 場所
- 国立病院機構 久里浜医療センター研修棟 大会議室
- 日程
- 2019年4月8日(月) 17:30~19:00
- プログラム
- マインドフルネスの基本と実践を川野泰周先生より、当院で実施している精神病圏の患者の方に対するマインドフルネス、依存/嗜癖の患者の方に対するマインドフルネスのプログラムの紹介を当院職員が行ないます。
① 特別講演 :「マインドフルネス 基本と実践」 川野泰周先生
② 依存/嗜癖行動のマインドフルネス : 当院職員
③ 精神病/統合失調症の方へのマインドフルネス : 当院職員

【 川野泰周先生プロフィール 】
●RESM新横浜睡眠・呼吸メディカルケアクリニック副院長
●精神保健指定医/日本精神神経学会認定精神科専門医/医師会認定産業医
●臨済宗建長寺派林香寺住職
1980年横浜市生まれ。2005年慶應義塾大学医学部医学科卒業。
臨床研修修了後、慶應義塾大学病院精神神経科、国立病院機構久里浜医療センターなどで精神科医として診療に従事。2011年より建長寺専門道場にて3年半にわたる禅修行。2014年末より横浜にある臨済宗建長寺派林香寺住職となる。
現在、寺務の傍ら、都内及び横浜市内のクリニック等で精神科診療にあたっている。
うつ病、不安障害、PTSD、睡眠障害、依存症などに対し、薬物療法や従来の精神療法と並び、禅やマインドフルネスの実践による心理療法を積極的に導入している。またビジネスパーソン、医療従事者、学校教員、子育て世代、シニア世代などを対象に幅広く講演活動を行っている。