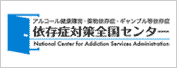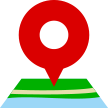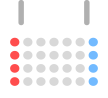インターネット依存治療研究部門
インターネット依存治療研究部門
(Treatment of Internet Addiction and Research, TIAR)
インターネット(以下、ネットと略)依存治療研究部門が、わが国で最初にインターネット依存やゲーム依存専門診療を始めてから10年が過ぎました。そこで、本部門が行っている治療や様々な活動に関する情報を刷新しました。また、情報ボックスを新設し、ネット・ゲーム依存に関連する情報を収載しました。
注 )なお、医学的にはネット依存は存在しませんが、一般には広く使われている用語です。そこで、本ページでは、ネットの過剰使用とそれに起因する問題が存在する状況をネット依存と呼ぶことにします。また、世界保健機関(WHO)が策定したICD-11に収載れている「gaming disorder」は、ゲーム症、ゲーム障害、またはゲーム行動症などと翻訳されています。しかし、本ページでは、一般によく使われていることから、これらに代わってゲーム依存という用語も使用しています。
診療について
- 日本で最初にネット・ゲーム依存の専門診療を開始しました。
- 数多くの患者さんの診療経験および既存の医学的知見をもとに、よりよい医療を提供しています。
(関連ページ:1. 受診の流れ / 2. 治療の実際) - ネット・ゲーム依存治療キャンプに参加できます。
(関連ページ:2. 治療の実際 8)治療キャンプ ) - ご家族に対する相談・支援プログラムを行っています。
(関連ページ:2. 治療の実際 6)ネット依存家族会 / 7) ネット依存家族ワークショップ) - オンラインの医療相談も行っています。
(関連ページ:オンライン医療相談・カウンセリングについて)
人材育成、啓発、研究など
- 厚生労働省の補助事業としてマンパワーの育成に取り組んでいます。
(関連ページ:3. 人材育成) - 啓発イベントや講演・研修等で、ネット・ゲーム依存の啓発・予防に積極的に取り組んでいます。
(関連ページ:6. 国際ワークショップ) - ゲーム依存に関わるWHOプロジェクトに最初から関わり、協力・支援してきています。
(関連ページ:5. WHOとの共同研究・事業) - 国内外の研究者などとともに、研究を積極的に進めています。
(関連ページ:4. 研究) - ネット・ゲーム依存治療に関する研修者を、国内外から受け入れています。
(関連ページ:8. 海外との事業)
医師・スタッフ紹介
- 松﨑 尊信医師
- 西村 光太郎医師
- 樋口 進名誉院長/医師
-
三原 聡子臨床心理士
-
前園 真毅精神保健福祉士
-
佐藤 広太看護師
-
北湯口 孝臨床心理士
-
岩本 亜希子精神保健福祉士
-
尾﨑 淳精神保健福祉士
臨床データの研究使用について
インターネット依存専門外来臨床データの研究使用について